
汎用のAndroid OSを搭載するのが主流になってからというもの、決済端末がどれも似たような格好(フォルム)になってどうにも面白みに欠けるーー本誌読者であればご理解いただけるであろうそんな感覚に、新鮮な風を吹き込んでくれそうな新しい決済サービスが発表された。着眼点からしてユニークなので、まずはその開発ストーリーから紹介していこう。

汎用のAndroid OSを搭載するのが主流になってからというもの、決済端末がどれも似たような格好(フォルム)になってどうにも面白みに欠けるーー本誌読者であればご理解いただけるであろうそんな感覚に、新鮮な風を吹き込んでくれそうな新しい決済サービスが発表された。着眼点からしてユニークなので、まずはその開発ストーリーから紹介していこう。
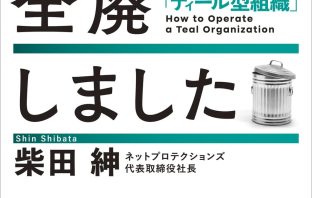
日本発祥で、世界に広がるBNPL(Buy Now, Pay Later)事業者の草分け的存在でもあるネットプロテクションズの社長を務める柴田 紳氏による著作である。ただし、日本では「後払い」とも表現されるBNPLビジネスのことを勉強してみようか、と本書を手に取ることはお勧めしない。代わりに本書で語られているのは、2000年創業のネットプロテクションズが2012年頃からの2020年頃までという長い検討期間を経てたどり着いた新しい組織のあり方である。

Stripeが生成AIを利用した「エージェンティックコマース」への対応を急いでいる。従来のEコマースは、販売する側も購入する側も人間だったが、ある程度自律的な動作も可能になってきたAIエージェントが、人間の意思を「代理」する場面が商取引においても起こりつつある。その際の課題や対応サービスの最新状況について、日本法人のストライプジャパンが説明した。

金融・決済事業のプロバイダー大手である米・ファイサーブが日本市場に進出する。三井住友カードと提携し、日本で初めて決済端末ソリューションの「Clover(クローバー)」を中小企業向けに展開。三井住友カードは法人口座を核とするB2B向けサービスの「Trunk(トランク)と組み合わせ、今後5年間で25万台の設置を目標に掲げる。

Binance Japan(バイナンス・ジャパン)は1月13日、東京都内で記者発表会を開催し、JCBブランドを搭載したクレジットカード「Binance Japan Card(バイナンス・ジャパン・カード)」の申込受付を同日から開始すると発表した。日本人が慣れ親しんだポイント還元の仕組みで暗号資産を付与することで、既存の決済サービスとブロックチェーン金融の接続を狙っていく。
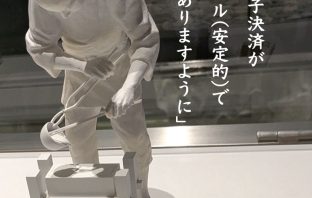
「今年も電子決済が、ステイブル(安定的)でありますように」。電子決済マガジンは、2026年もじっくりと日本のキャッシュレス化を応援していきます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

2025年も残りわずか。電子決済マガジンが選ぶ今年一番のニュースは、Perfumeのコールドスリープでもなく熊大量出没でもなく、やっぱりこれだった。今年、会場内の「全面的キャッシュレス決済」にチャレンジし、多くの会社にとって仕事納めとなった12月26日の前日にギリギリ滑り込みで集計データを公表してくれた万博協会に敬意を表したい。

法人間(B2B)でのカード決済を提供する新しいスキーム「請求書カード払い」に関連し、その健全な普及拡大を目的にキャッシュレス推進協議会が「請求書カード払い取引ガイドライン」を公表した。これを受けて、公表当日の12月26日にはクレジットカード会社など請求書カード払いの関連事業者20社超が参加して「請求書カード払い協会」が設立された。まだまだなじみの薄い請求書カード払いの特徴とガイドラインの概要、新協会のミッションを整理して解説する。

福岡を本拠とする「TRIAL(トライアル)」の小型スーパー店舗、「TRIAL GO(トライアル・ゴー)」がこの11月に都内初出店を遂げた。トライアルではハウス型プリペイド決済サービスの「SU-PAY(スーペイ)」を提供しているが、この追加サービスとして「顔認証決済」が利用可能になっており、TRIAL GOは全店で対応している。ということで、都内初出店のTRIAL GOでさっそくSU-PAYの顔認証決済を試してきた。

ビザ・ワールドワイド・ジャパン(以下、「Visa」という)は12月10日、東京都内で記者説明会を開催し、2026年2月から「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」を全国で展開すると発表した。登壇したビザ・ワールドワイド・ジャパン・代表取締役社長のシータン・キトニー氏(写真)は、来年、2026年以降にVisaが注力する領域として、3つの分野を挙げた。

FIDOアライアンスは12月5日、毎年恒例の記者説明会を東京都内で開催し、今後はパスキーの開発と普及啓発に向けた経験を生かして、新たに「デジタルクレデンシャル」の領域に取り組んでいくことを表明した。一方、日本国内でも大規模な不正アクセスや不正取引に見舞われた証券会社をはじめ、パスキーの導入が加速している。

幕張メッセ(千葉市美浜区)で2年ごとに開催されている鉄道技術展が、今年は土曜日を含む11月26日から11月29日までの4日間に渡って開催された(「第9回鉄道技術展2025」)。好天にも恵まれ4日間で3万9,120人が訪れた同展示会会場から、いつもの“電子決済マガジン視点”にて、最新の顔認証改札機や鉄道業界で活躍する決済システムなどをレポートする。

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下、「万博協会」)は11月17日、2025年日本国際博覧会(以下、「大阪・関西万博」)にて万博史上初めて実施した「全面的キャッシュレス決済による会場運営」に関して、その効果検証結果をまとめた報告書を公開した。万博協会は同日に記者説明会を開催し(写真1)、報告の要旨と、今後のさらなるキャッシュレス推進に向けたヒントを提言した。

東武鉄道と日立製作所は11月13日、東京都内で記者発表会を開催し、これまで指静脈で提供してきた生体認証サービス「SAKULaLa(サクララ)」を新たに顔認証に対応させ、同日から東武宇都宮線の鉄道改札に導入したことを発表した。2026年度からは決済端末のJET-S端末でも顔認証決済が利用できるようにするほか、オフィスの入退管理などでの導入を本格化させる。

東京・有明の東京ビッグサイトで10月31日から11月9日までの期間、「Japan Mobility Show(ジャパンモビリティショー)2025」が開催されている。今年はなんと新作が公開されたばかりの映画『TRON(トロン)』シリーズに登場する「ライトサイクル」が展示されていると聞きつけ、電子決済の次にトロン好きの筆者としては慌てて馳せ参じることになった。