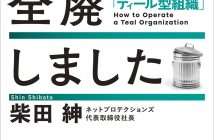4月10日、米国Alphabet傘下のWaymo(ウェイモ)社と、GO、日本交通の3社は、東京港区の高輪ゲートシティ駅にて、日本へ初めて輸入したWaymo車両を報道機関に公開し、有人での走行デモンストレーションを行った(写真1)。今後、東京都の7つの区を対象として、まずは運転手による手動運転方式からテスト導入を開始するという。

写真1 フォトセッションの模様。写真左から、GO 代表取締役社長の中島 宏氏、日本交通 代表取締役社長の若林 泰治氏、Waymo社 シニアディレクター 事業開発部門・パートナーシップ部門責任者 ニコール・ガベル氏、日本交通 取締役 兼 GO 代表取締役会長の川鍋 一朗氏、東日本旅客鉄道 代表取締役社長の喜㔟 陽一氏
テストの第1段階は、有人の手動運転から
Waymo(ウェイモ)は米国の4都市(カリフォルニア州サンフランシスコ、ロサンゼルス、アリゾナ州フェニックス、テキサス州オースティン)で無人での完全自動運転タクシーサービスを提供中。ジョージア州アトランタ、フロリダ州マイアミ、ワシントンD.C.でも近日中にサービスを開始する予定である。
日本でも将来的に、無人・完全自動運転の形態によるサービス提供を目指しており、昨年12月にはGO、日本交通の2社との間で、東京でWaymoの自動運転技術「Waymo Driver」のテストを実施するために戦略的パートナーシップを締結した。
今回、公開されたのはその第1号として日本へ輸入されたWaymo車両(写真2〜5)。テストの第1段階は無人ではなく、日本交通の運転手が手動で運転する方法により、東京都の7つの区(港区、新宿区、渋谷区、千代田区、中央区、品川区、江東区)を走行する計画となっている(動画)。
その後、テストの第2段階では、運転手がいつでもハンドルを握れる状態での自動運転へ移行。米国で提供されているような無人・完全自動運転はさらにその次の第3段階に位置付けられている。
【動画】Waymo車両の報道機関向け公開(2025年4月10日@高輪ゲートシティ)

写真2 日本で初公開されたWaymo車両。米国で走行しているものと同一車両だが、補助ミラーの形状など日本の環境にかなう形で調整を行ったという

写真3 頂上部は360度のライダー(LiDAR)とビジョンシステムを搭載。前面には長距離カメラとレーダーがある


写真4、5 フロントとリアの両サイドには、それぞれ周囲用のライダー(前側のみ)とビジョンシステム、レーダーを搭載
「Waymoを利用した際の決済手段は、果たしてどのような形になるのか?」「日本では『GO』のアプリからWaymoを呼んで、支払いも『GO』のアプリからオンライン決済で??」などと夢想しながら報道公開に参加した記者だったが、そのあたりが具体的になってくるのはもう少し未来の話となりそうだ。

写真6 Waymo社 シニアディレクター 事業開発部門・パートナーシップ部門責任者 ニコール・ガベル氏。「米国以外でWaymoが走行するのは今回が初めてのことで、日本の先進性を示している。米国でWaymoは毎週20万回走行している。子供の送り迎えなど人々の生活にお使いいただき規模が大きくなっており、ビジネスになっている。日本では、道路標識も使えば交通ルールも違うので、まずは手動で運行してデータを収集するところから始めたい」

写真7 日本交通 取締役 兼 GO 代表取締役会長の川鍋 一朗氏。「1年前に『アメリカですごいのが走ってるらしい』と聞き、フェニックスへ乗車しに行った。アプリを押したら向こうからこの車が近づいてきて、運転席には本当に誰もいない。透明人間のようにハンドルが勝手に動いている。3回乗車し、この道のプロとしてアラを探したが、なかった。その瞬間、『これは絶対に日本のためになる。少子高齢化などで労働力不足になる日本の足になる』と確信した。絶対の安全性を持って、一歩一歩進んでいきたい」
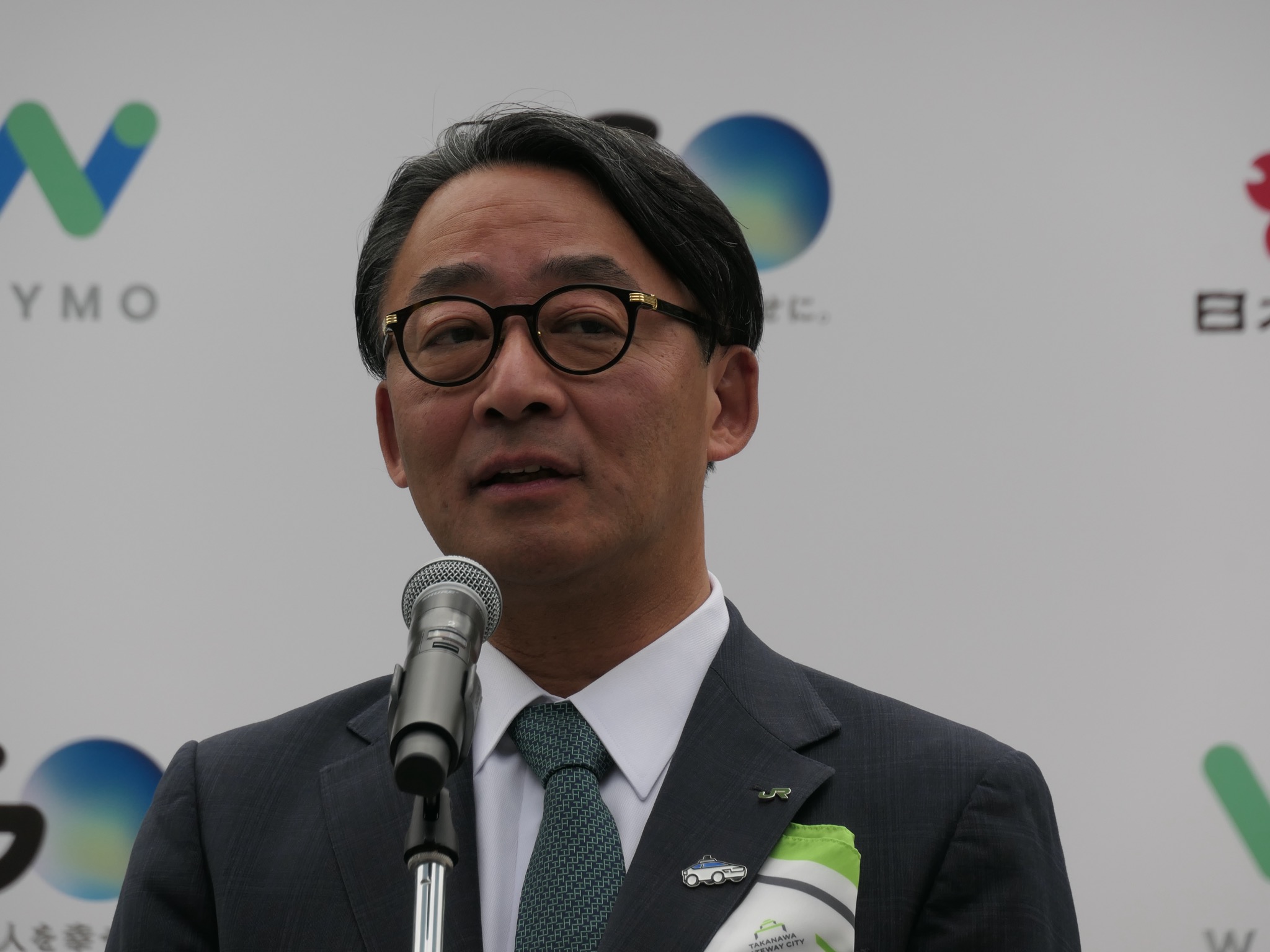
写真8 来賓として登壇した東日本旅客鉄道(JR東日本) 代表取締役社長の喜㔟 陽一氏。「この高輪ゲートウェイシティは、さる3月27日に〝まちびらき〞したが、この地は150年前に日本で初めて鉄道が始まった場所であり、日本のモビリティのイノベーションの地ともいえる。その地で、Waymoと一緒に次のページを開かせていただけることはJR東日本グループとしても光栄なことで感慨深い。Waymoをこれからも進化し続けるSuicaと結びつけることによって、ストレスフリーのシームレスなサービスとして毎日私どもの鉄道をご利用いただいている1,600万人のお客様にお届けしたい」
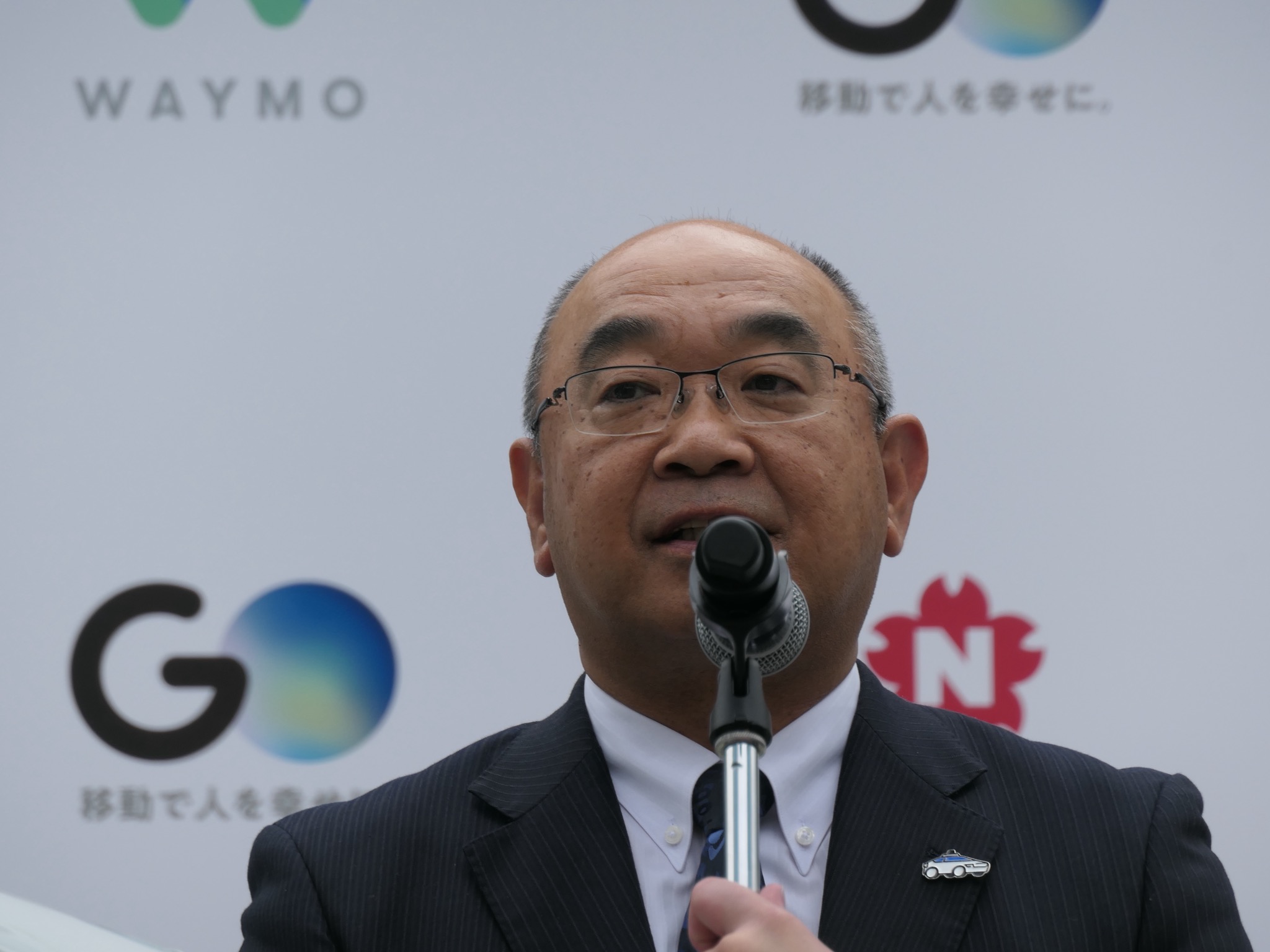
写真9 日本交通 代表取締役社長の若林 泰治氏。「(自動運転タクシーが)労働力不足を補完する役割になると、社会への貢献もできる。これこそが、タクシー会社が参加する意義だと思っている」

写真10 GO 代表取締役社長の中島 宏氏。「いよいよ車両がやって来たという思い。労働人口の低下という課題がある中で、まずは東京で始めるが、他の地域にも広げていくことが必要になると考えている。まずは東京で社会的受容性を育み、今後も段階的に取り組んでいきたい」