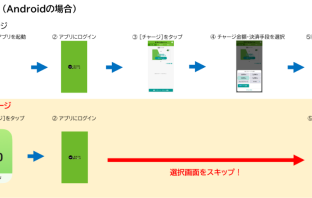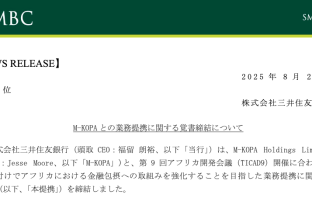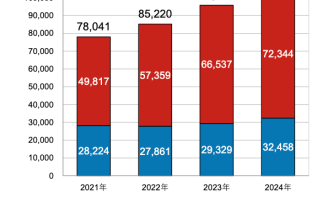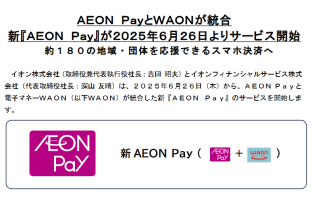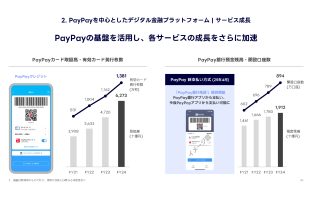NTTドコモ、三井住友信託銀行、住信SBIネット銀行の3社は12月19日、住信SBIネット銀行の商号を、2026年8月3日から「株式会社ドコモSMTBネット銀行(以下、「ドコモSMTBネット銀行」という)」に変更することを決定したと発表した。同商号変更は関係当局の認可を前提としている。また、住信SBIネット銀行のさらなる成長と、共同経営におけるドコモおよび三井住友信託銀行のパートナーシップ強化を目的として、2025年12月25日に住信SBIネット銀行の資本再編を実施する。さらに、各社の経営資源を活用した新たな価値創出に向けた協業施策を順次開始する予定。